ケア現場の“リアル”な時間割事情「シフトの自由度はどのくらい?」
こんにちは。ケア魂デザイン編集部です。
今日は求職者さんからよく聞かれる質問、「シフトの自由度って実際どのくらいあるんですか?」について、ちょっと掘り下げてみたいと思います。
シフト=自由?それともパズル?
ケア業界のシフト調整は、一言でいうと「テトリス」。
ピタッと揃うと気持ちいいけど、揃わないと頭を抱える。
「午前は通院付き添いが入るから、午後は早めに帰りたい」
「子どもの参観日があるから、その日は休みたい」
「夜勤は連続で入るときついから、間をあけてほしい」
スタッフ一人ひとりの希望を反映しながら、利用者さんの生活リズムを崩さないように調整する。
これがケア現場の“シフト芸術”です。
現場の工夫① 「希望シフト表=お願いポスト」
ある事業所では、休憩室に「希望シフトボード」が設置されているそう。
スタッフはそこに「〇日は休み希望!」「この日は夜勤NG!」とペタペタ貼る。
まるで小学生の“お願いポスト”みたいですが、不思議と和やかな雰囲気になるのだとか。
「え、○○さんもその日休み?じゃあ私出るよ!」なんて助け合いも自然に生まれるそうです。
現場の工夫② 「推し活シフト」って何!?
ユニークな取り組みとして聞いたのが、スタッフの“推し活”優先シフト。
「推しのライブがある日は必ず休み」
「新作ゲームの発売日は、夜勤明けにして午前中は寝たい」
一見わがままに聞こえるけど、推し活がモチベーションになり、仕事のパフォーマンスが爆上がりするならアリじゃない?という発想です。
現場のリーダーはこう言います。
「人って“好きなこと”を犠牲にすると疲れるんですよ。推し活優先シフトは、結局みんなの笑顔につながってます」
現場の工夫③ 「くじ引きナイトシフト」
夜勤はどうしても敬遠されがち。
ある施設では、思い切って「くじ引き制」にしたそうです。
「公平さ」と「運ゲー感」で、不思議と不満が減る。
「うわ~当たっちゃった!」なんて言いながらも、意外と笑いながら夜勤に入れるとか。
もちろん、体力的に難しい人は免除。
無理をさせない+みんなで分担が前提の工夫です。
求職者が気になる「自由度」のホントのところ
じゃあ結局、自由度ってどのくらいあるの?
結論を言うと…
「現場次第。でも“ゼロ”ではない」です。
ケア業界は「利用者さんの生活ありき」だから、100%自由にはできません。
ただし、最近はスタッフのライフスタイルを尊重する施設も増えてきています。
・子育て世代には「学校行事優先」シフト
・ダブルワークの人には「曜日固定」シフト
・趣味や推し活重視の人には「特別休暇」
…などなど、工夫次第で自由度は広がるのです。
シフトの自由度=チームワークのバロメーター
面白いのは、シフトの自由度って“チームの空気”に比例すること。
ギスギスした現場だと「またあの人休み希望かよ…」と不満が出やすい。
逆に和気あいあいした現場だと「いいよ、私入るから安心して休んで!」と声が飛ぶ。
つまり、自由度の本質は“人間関係の余白”なんです。
カレンダーのマス目だけを見ていると苦しくなるけど、人と人との気遣いがあると、シフトも驚くほど柔軟になるのです。
未来のシフトはAIが組む?
最後にちょっと未来的な話。
最近はAIでシフトを自動作成するシステムも登場しています。
「希望休+人員配置+利用者ニーズ」を一瞬で分析し、最適解を出してくれる。…はずなのに、現場からはこんな声も。
「AIが作ったシフトは、数学的には正しいけど人情が足りない!」
「“○○さんの誕生日だから休ませたい”とかはAIにわからない(笑)」
結局のところ、シフトは人の思いやりで回っているんですね。
まとめ
「シフトの自由度はどのくらい?」という質問への答えは、“現場の人間関係と工夫次第で、自由度は大きく変わる”です。
・お願いポストでみんなの希望をシェア
・推し活シフトでモチベーションUP
・くじ引きナイトで笑える工夫
・AI+人情で未来型シフトへ
シフトはただのカレンダー調整じゃなく、現場の温度感を映す鏡。
自由度の高さ=働きやすさ、と言ってもいいかもしれません。
求職者の皆さん、ぜひ面接で「ここはどんな工夫をしていますか?」と聞いてみてください。
そこに現場のリアルが隠れていますよ。

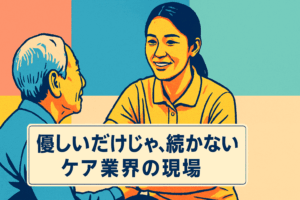


コメント