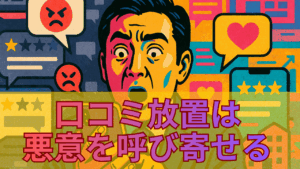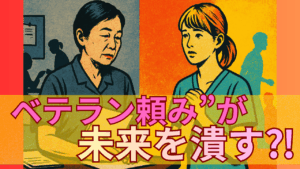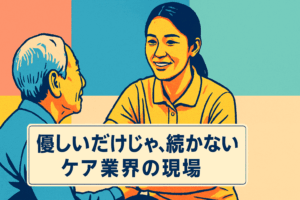「サイトが止まったまま=終わっている事業所」採用・集客を遠ざける落とし穴
「御社のホームページを見ましたが、最新のお知らせが3年前で止まっていましたね」
もし利用者のご家族や求職者からこう言われたら、ドキッとしませんか?
ケア業界でありがちな失敗のひとつが、事業所のサイトを更新せず放置してしまうことです。
施設案内やサービス内容はそれなりに整っていても、「お知らせ」や「活動報告」が数年前から動いていない。この時点で利用検討者も応募者も、不安や不信を抱いてしまいます。
「ここに任せても大丈夫なのか?」
「スタッフはもう足りているから更新していないのか?」
「終わっている事業所では?」
そんなマイナスイメージが、ほんの数分の閲覧で刻まれてしまうのです。
なぜ「終わっている事業所」に見えるのか
介護や福祉の現場は、利用者やその家族にとって安心感が最優先です。
にもかかわらず、事業所のサイトが古びたままだと、次のように思われてしまいます。
「ここは本当に今も運営しているの?」
「人手不足で余裕がなく、サービスの質も落ちていそう」
「時代に取り残されている印象」
採用においても同じです。応募者は必ずといっていいほど事業所のホームページを確認します。
そのとき「最後の更新が数年前」で止まっていたら「ここで働くのはやめよう」と考えるのは自然なことです。
採用にも集客にも直結するリスク
更新の止まったサイトは、信用の欠如=人も利用者も集まらないという結果に直結します。
求職者が応募をやめる
→「古臭い」「活気がない」と感じ、求人票を見ても興味を失う。
利用者の家族が別の事業所に流れる
→「活動が見えない=安心できない」と判断される。
紹介・連携が減る
→ケアマネや病院担当者も「ここは情報が出ていないから不安」と他事業所を紹介。
つまり、「サイトを放置する=採用と集客の機会を失う」ことを意味します。
よくある言い訳とその代償
なぜケア業界でサイトが放置されやすいのでしょうか?
更新する人がいない
管理者や事務長が「やらなきゃ」と思いながらも日常業務に追われ、後回しになる。
更新する内容がわからない
「特別なイベントやニュースがないと意味がない」と思い込み、結局何も発信しない。
制作会社に頼むしかなく、コストがかかる
内部で触れない仕組みになっていて、小さな更新も大ごとになる。
この結果、「終わっている事業所」に見えてしまうのです。
実際には頑張って現場を回していても、外からはそうは映りません。
小さな更新で“生きている事業所”を示す
重要なのは、小さくても続けることです。大きなイベントやリリースは不要。
求職者も利用者も、見たいのは「今も動いている証拠」だけです。
季節のご挨拶(年末年始・夏季休業など)
日常の取り組み(レクリエーション・リハビリ風景・地域交流)
スタッフ紹介や資格取得の報告
感染症対策や研修の実施状況
こうした情報が載るだけで、「安心して任せられる」「働いてみたい」と感じてもらえます。
更新を止めた事業所の末路
逆に言えば、サイト更新を放置した事業所は次のようなリスクを背負います。
応募ゼロのまま求人広告費だけが膨らむ
利用者の新規契約が減り、稼働率が下がる
「紹介したくない事業所」というレッテルを貼られる
「忙しいから仕方ない」と思っていたことが、気づけば採用難・集客難の原因になっているのです。
続けられる仕組みを作る
大事なのは「頑張って更新する」ことではなく、続けられる仕組みを用意することです。
スタッフ持ち回りで投稿する仕組み
管理者だけでなく、現場のスタッフが写真付きで短文を発信する。
週1回の更新をルール化
完璧を求めず「今月の様子」を出す習慣をつける。
誰でも更新できるCMSにする
WordPressやノーコードツールなら、ITに不慣れでも簡単に更新可能。
このように仕組み化することで、更新が止まるリスクを減らせます。
採用も集客も「更新」で差がつく
ケア業界はどこも人手不足。利用者の獲得も競争が激しい。
そんな中で「サイトが更新されていない」というだけで、他の事業所に後れを取るのはあまりに惜しいことです。
「終わっている事業所」と思われるか、
「いまも活動的で、信頼できる事業所」と見られるか。
その分かれ目は、ほんの小さな「更新」にあるのです。
今日からでも遅くありません。
小さな発信を積み重ねて、採用でも集客でも選ばれる事業所を目指しましょう。