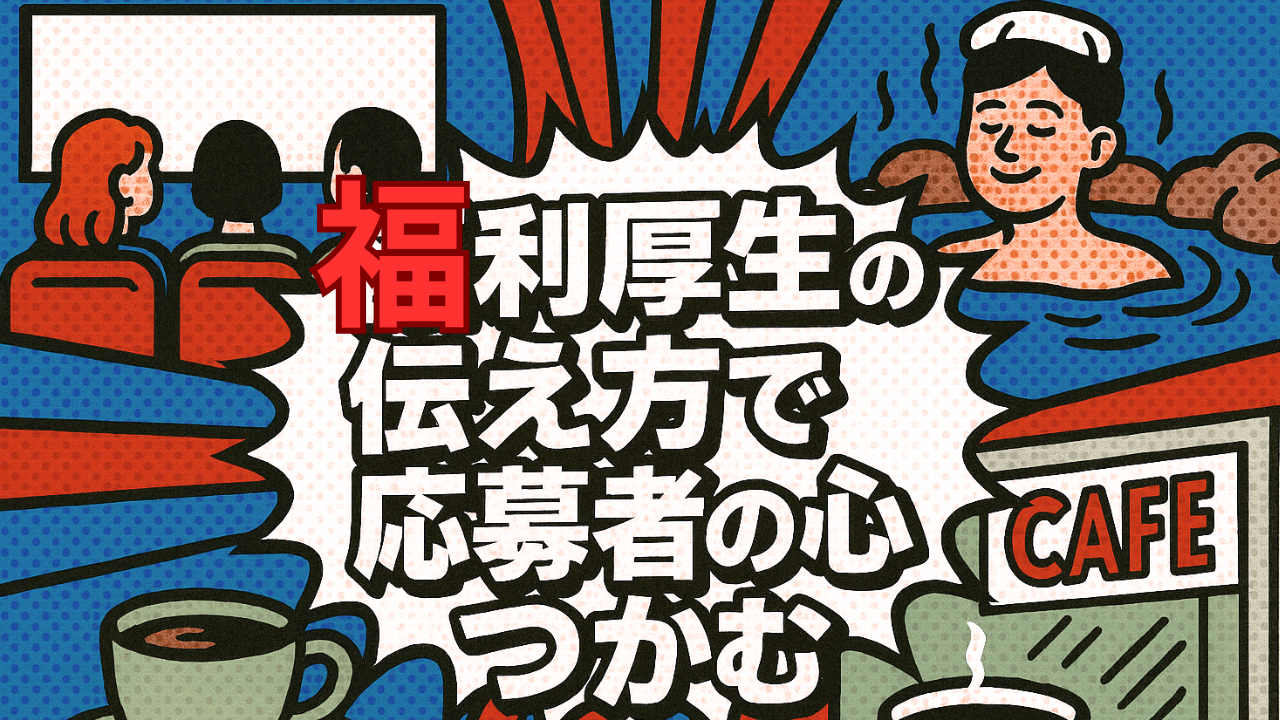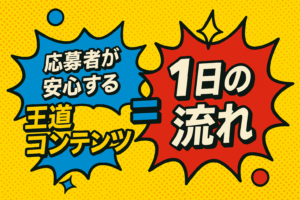ケア業界だからこそ“響く”アピール術
「福利厚生」と聞くと、どうしても“堅い項目一覧”を並べるだけになりがちです。
でも、応募者の心を動かすのは「制度の名称」ではなく、「その制度でどんな毎日が待っているのか」というイメージ。
ケア業界(訪問看護・介護・デイサービスなど)で働きたい人にとって、給与や休日はもちろん大切ですが、「ここで働いたら自分の生活がちょっと楽しくなる」「長く安心して続けられる」という安心感と期待感こそ、応募を後押しする力になります。
では、採用サイトに福利厚生を載せるとき、どう表現すれば“心に刺さる”のでしょうか?
今回は、従来の「福利厚生=チェックリスト」的な表現を卒業して、ユニークかつ親しみのある見せ方を紹介します。
「制度名」より「体験シーン」で伝える
たとえば「資格取得支援制度」と書くだけでは味気ないですよね。
応募者は「で、実際どうなるの?」と想像できずに終わります。
そこで一歩踏み込んで、こんな表現に変えてみましょう。
「仕事帰りにオンライン講座を受講し、受験料は会社が全額サポート」
「スタッフの○○さんも昨年この制度を使ってケアマネ試験に合格!」
つまり、“その制度を使ったら自分の未来がどう広がるか”を具体的に描くことが大切です。
応募者が「ほっ」とする福利厚生を前面に
ケア業界の求職者は「人のために動く」やさしい人が多い反面、燃え尽きやすい傾向もあります。
だからこそ「休める仕組み」「リフレッシュできる工夫」は強い訴求ポイント。
✅「有給休暇がとりやすい環境」ではなく
▶「子どもの行事や家族の予定に合わせて休みを調整できます」
✅「リフレッシュ休暇あり」ではなく
▶「誕生日には有給+ケーキでお祝い」
✅「福利厚生倶楽部に加入」ではなく
▶「映画館・温泉・カフェなど、週末の楽しみに使える優待多数」
制度を“人の温度感”に落とし込むだけで、応募者は「ここなら大切にされそう」と直感します。
「数字で見える安心感」も効果的
人によっては「なんとなく良さそう」より「データで安心したい」タイプもいます。
そんなときは数字を交えると説得力が増します。
「有給取得率◯%」
「平均残業時間:月◯時間」
「産休・育休取得実績:過去3年間で◯名」
数字は嘘をつきません。しかも、数字は応募者にとって“会社の姿勢”を測る物差し。
「働きやすさを本気で守っている」ことを数字で見せるのは、ケア業界こそ必要な工夫です。
現場の声を混ぜると“生きた制度”になる
「制度はあるけど実際には使えない」というのは、ケア業界ではありがちな悩み。
だからこそ、スタッフの声を入れると説得力が跳ね上がります。
「この前、子どもの急な発熱で休ませてもらいました。代わりに先輩がフォローしてくれて助かりました」
「資格取得支援のおかげで、念願のリハビリ資格に挑戦できています」
“制度を使った人の声”は、何よりリアルで、応募者の想像を後押しします。
福利厚生を「ストーリー」で紹介する
ただ並べるのではなく、物語調にするのもユニークで親しみやすい方法です。
例)
「ある1日の流れ」ページに、こう差し込むのです。
18:00 退勤。今日は映画館の割引チケットを福利厚生でゲット!同僚と仕事帰りに映画を観に行きました。
翌朝もスッキリ出勤。
こうした“日常の1コマ”を描くと、応募者は「ここで働いたら楽しい毎日が待っている」とイメージしやすくなります。
「小さな工夫」も立派な福利厚生
大手企業のような豪華な制度はなくても大丈夫。
ケア業界の小規模法人こそ、“小さな工夫”を大切にアピールできます。
●毎月のお誕生日会
●おやつタイムに地域のお菓子を差し入れ
●みんなで作った“ありがとうカード”の掲示板
●「お金はかけられないけど、人を思いやる文化」は、大手では真似できない強みです。
応募者は制度そのものより「人間関係が温かそう」という印象を重視するからです。
福利厚生は“会社の人柄”を映す鏡
福利厚生は単なる制度紹介ではなく、「この会社はスタッフをどう扱っているか」を映す鏡です。
●制度名の羅列ではなく、体験を描写する
●応募者が「ほっ」とするポイントを強調する
●数字や現場の声を混ぜて安心感を出す
●日常のストーリーに織り交ぜる
小さな工夫も立派な強み!
これらを採用サイトに取り入れるだけで、応募者は「ここで働きたい」と自然に感じます。
福利厚生を通じて伝えるのは、制度そのものではなく、「あなたを大切にする会社です」というメッセージなのです。